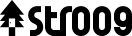私は元々大学で木材や木構造の基礎研究に取り組んできた流れで構造設計に携わるようになり現在に至る。この間はちょうど木造建築産業を取り囲む状況が世の中の潮流に相まって劇的に変化を遂げてきた時期であり、私は偶然にもその過程を間近で見てきたと思う。このようなバックグラウンドをもつ自分のような人間の視点から、まだ世の中にない「あったらいいな」を考えてみたいと思う。
近年まで住宅を主戦場にしていた木造建築が、多種多様な建築へ用途を拡大する中で、鉄やコンクリートで作っていた建築の安易な置き換えとして木造を考えないことが重要なポイントだと思っている。木材は強度をはじめとする材料の特性が鉄やコンクリートとは全く異なる材料であるから、同じことを木でやろうとすれば、当然あちこちに上手くいかないことが出て来るはずである。木造で挑戦するのだから、建築とはこういうものだ、という既成概念をとっぱらって考えてみよう、といった思い切りが、これまでにない「こういうのいいな」を実現する可能性を秘めているように思う。
構造に関しても、自身が普段知らず知らずのうちにさまざまな既成概念にとらわれていることを自覚した上で、必要に応じてこれを取り除いて考えることができることは重要だと考えている。例えば構造設計者は建築の構造を考えるときに、普通は柱や梁、壁といった要素を組み合わせて構造体を構成しようと考える。これらの構造要素は先人たちが構造の中の力の流れを解き明かし、より明快で理に適った構造を追求する努力の積み重ねの結果たどり着いたものであるが、自然の作り出す造形に目をやれば、それらの構造はこのような人為的に明快な役割を与えられた要素ではおおよそでき上っていないものばかりであることがわかる。人工的な構造物が明快な力学状態を標榜して作られることの意義は十分理解しているし、仕組みの不明快な複雑で混沌とした構造を個人的にはあまり美しいとは思わない。言いたいことは、例えば柱と梁と壁で建物を作るということを前提とするのをやめてみても別の構造システムができる可能性もあるのではないか、というようなことである。これまでの歴史の積み重ねによって構築されてきた構造技術は言わば設計者が身に着ける型のようなもので、これから一歩踏み出す時には、この型を十分に体得した上で、これを再構築するようなプロセスが必要だと考える。ストローグ社屋は柱とも梁とも壁とも異なる、それらの役割を全て果たす名もなき1種類の構成要素から構造体が出来上がっている。

ストローグ社屋 CLTパネルによって組みあがった架構
新しく創造された構造システムが「あったらよい」ものとしての意義を得るためには、それが何らかの合理性を高めるものでなければならない。構造を考えるときは力学的な合理性以外に、経済性、建築空間との親和性等を総合して判断することになるが、架構を表現として見せることが比較的多い木造では、力学的な合理性だけでなく、建築空間との親和性に対する比重も大きい。できるだけ少ない構造材で架構を構成することが単に最適というわけではないのである。人類はアーチ構造、トラス構造、梁構造、シェル構造など、ある特徴的な応力状態を作り出す架構の形態に対して名前をつけてこれらを分類してきたが、実際にはこれらの架構形態同士の間には無限のグラデーションがあり、このどこかにその建築にとって本当に美しいと呼べる架構が存在していると思っている。接合が構造体の性能を支配する木造では、接合の合理性も重要である。シネジック社屋では立体トラスによる架構のうち、3次元的な角度で複雑に取りついてくる部材をパネルに置き換えることで、一箇所に集まってくる部材を減らしてビスによる単純な接合を可能とし、線材による立体トラスとはまた少し風合いの異なる特徴的な空間を作り出した。

シネジック社屋 集成材とCLTパネルによる立体架構
木造建築は高層化や大規模化にこれからも益々挑戦し続けるであろう。この過程の中で、これまでにない「こういうのいいな」がどんどん誕生するのではないかと期待される。
KMC/蒲池健

2007年 東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了
2007年-2013年 東京大学アジア生物資源環境研究センター 特任研究員を経て特任助教
2013年-2016年 株式会社 山田憲明構造設計事務所勤務
2016年-現在 KMC主宰
日本建築学会編 木質構造接合部設計マニュアル 共著
日本建築学会編 木質構造基礎理論 共著
日本建築学会編 木質構造部材・接合部の変形と破壊 共著
日本住宅木材技術センター 木造軸組工法中大規模建築物の許容応力度設計 共著
日本建築学会木造構造系委員会、日本住宅木材技術センター委員等を歴任